【東進衛生予備校】模試の種類と活用方法について【須賀川駅前校】
この記事を書いた人:水野
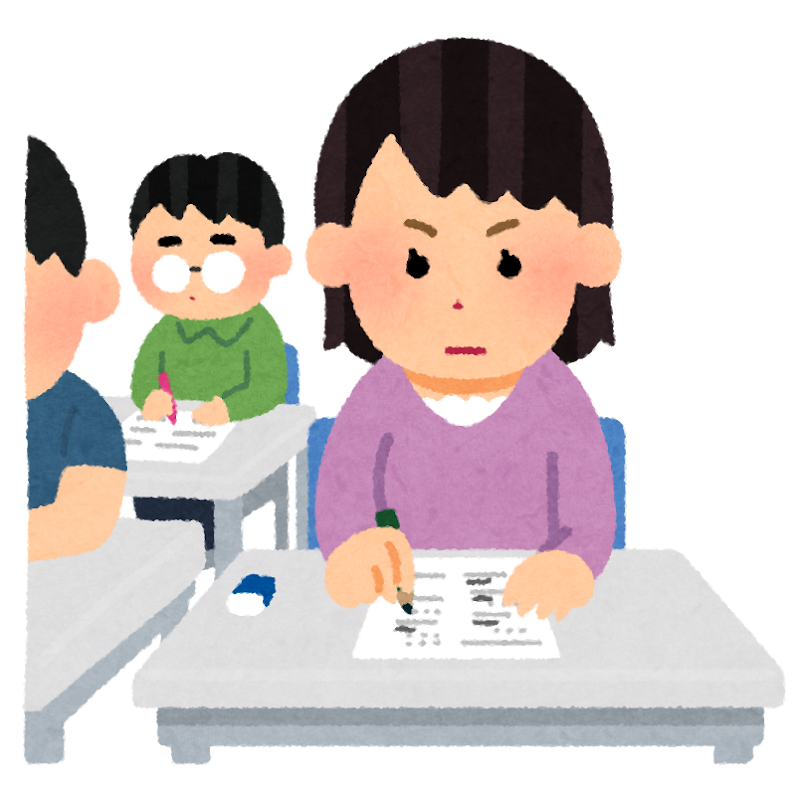
CONTENTS
はじめに
みなさん、こんにちは!
須賀川駅前校の水野です😊
9月に入ってもまだまだ暑い日が続きますね💦
猛暑日に慣れてしまったせいか、最高気温が30℃などの日はまだ過ごしやすい方だと感じてしまっています😅
引き続き、気温の高い日は外での活動時間を極力減らしたり、体を冷やすために首にコールドリングを巻いたりと対策しておくのが良いですね。
さて、今回は学校や塾で受ける「模試」について掘り下げてみたいと思います。
問題の難易度が高く、なかなか復習まで手が回りづらいのが「模試」の特徴です。
時間をかけて受験した模試をしっかりと活用していきましょう!
模試について
(1)模試の種類
まず、高校生が受ける模試にはどのような種類の模試があるのでしょうか?
分類をざっくりと分けると以下のようになります。
①国数英の基礎力を測る模試(東進の「大学合格基礎力判定テスト」)
②現学年レベルのマーク模試
③共通テスト、私大レベルのマーク模試
④現学年レベルの記述模試
⑤二次、私大レベルの記述模試
だいたいの分け方なので、もっと細かく分類できるかもしれませんが、まず模試は「マーク模試」と「記述模試」に分かれます。
①~③は「マーク模試」と呼ばれていて英検などでも用いられています。
解答方法はマークシートの正しい解答番号を鉛筆で染めていくものです。
数学では計算過程を描く必要は無いですし、英語では英作文や和訳問題などが出題されることはありません。
所定の印を丁寧に塗りつぶさないと、機械がマークした箇所を読み込めない場合があります。
また、マークする場所がずれてしまうと、それ以降の問題が全てずれて不正解となってしまいますので、十分に気をつけてマークする必要があります。
(例:問題番号⑤にマークする予定が、1つ下の問題番号⑥にマークしてしまった)
そして④、⑤の「記述模試」は先程のマーク模試で出題されないと書いた「数学の計算過程を記述する問題」「英語の英作文や和訳問題など」その他の科目でも、記述が必要とされる問題となります。
(記述模試でも一部、選択問題が出題されます)
(2)①~⑤の模試の違いについて
①東進「大学合格基礎力判定テスト」
国語、数学、英語を「基礎、標準、応用」レベルで分野別に分類して問題を解くため、自分の基礎力をしっかり把握することができます。
②「現学年レベルのマーク模試」
基本的に習った単元・分野からの出題からの出題となるため、学習範囲の定着度チェックと捉えましょう。
ただ、定期考査よりも試験範囲が広かったり、難易度が上がっていることも多いので油断はできません。
③「共通テスト、私大レベルのマーク模試」
基本的に受験生対象で、難易度が②よりも高い模試となります。
基礎の定着ができていないと対応できない問題も多いので、教科書レベル、問題集レベルの問題は解けるようにトレーニングしておきましょう。
④「現学年レベルの記述模試」
日頃から記述問題の対策ができているかが問われます。
例えば「数学」では、答えを出すまでの計算過程や条件の設定、範囲の指定など…論理的に答えに導けるかによって大きく点数に差がつきます。
⑤「二次、私大レベルの記述模試」
かなり難易度が高い模試となるため、共通テストレベルである程度、得点が取れる力が無いとなかなか点数は伸びないかもしれません。
ただ、第一志望の大学レベルを把握したり、問題の傾向を掴むためにも、点数にこだわらず、早めの時期から挑戦しておくことがお勧めです。
(3)模試の活用方法
受験するだけでもかなりの時間と体力を使う模試ですが、終了後は意外に振り返りをせずにいることも多いかと思います。
学校の部活、行事、定期考査・・・などなど、高校生はやるべきことがとてもたくさんあるので、どうしても模試の復習は後回しになってしまいがちです。
そこで、定期考査や部活の大会直前期などを避けて、事前に「いつ模試の復習をするのか」を年間のスケジュールの中に組み込んでおくとよいでしょう。
夏休みや冬休み、GWや年末年始など、長期休み期間は特に時間を取りやすいかと思います。
そして、どうしても復習に手が回らない時は「科目」と「単元」を絞って復習することも大切です。
例えば「数学の二次関数」「英語の長文のうち大問1つ分」「現代文の小説」…など、特に苦手な科目、単元から手を付けていけば、自分にとっては伸びしろのある分野から学習を始められます😊
定期考査が間近にせまっている方も多いかと思いますが、考査が落ち着いたらぜひ「模試の復習」を取り入れてみてください(`・ω・´)
おわりに
今回は「模試」に注目して記事を書かせていただきました。
「模試の活用」は忙しい高校生にとっては、なかなか難しいことかと思いますが、自分の現状を把握して今後の方針を定めるため、ぜひ上手に活用していきたいですね!
それでは、ここまでご精読いただき、ありがとうございましたm(_ _)m